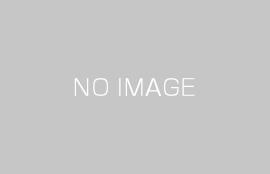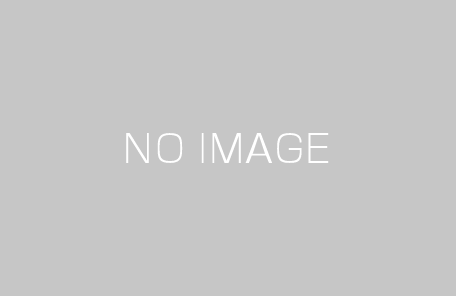もっと通じる英語に!イントネーションで大事なのは使えること
3月に『もっとイギリス英語でしゃべりたい! UKイントネーション・パーフェクトガイド』の新装版が出ます![]()
予告編動画↓↓
で、この本で言いたかったのは、
1)イギリス英語(BE)のイントネーションを詳しく解説するという
ことと、
2)イントネーションはただ真似るだけじゃあ意味ない、使いこなせるようになること、
の2つ![]()
![]()
1では、母音や子音以上に、BEらしさの元となるイントネーションの特徴を浮かび上がらせること![]()
この本で特に詳しく書いたのは、
降昇調
↘↗ こういう下がって上がるトーン。
これBE(イギリス英語)ではすごく使われます![]()
![]()
でもAE(アメリカ英語)ではあまり出てこない![]()
![]()
AEは単純な上昇調が多いのです
![]() アゲアゲ
アゲアゲ
だから降昇調に習熟することが、BEらしさを生み出すわけです![]()
とりわけ、降昇調の中でも
分離降昇調
というのがBEっぽい![]()
![]()
↘と↗が分かれて出てくるパターン![]()
![]()
例えばこんなのです。
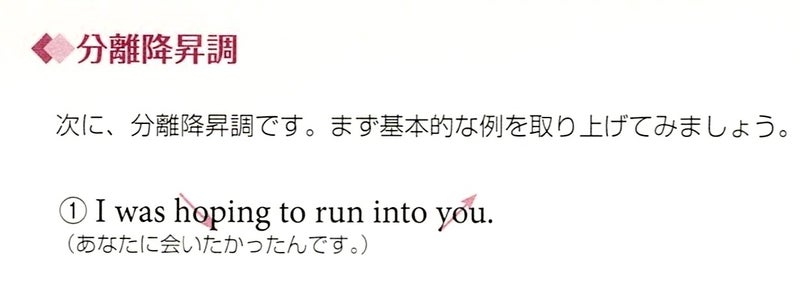
『もっとイギリス英語でしゃべりたい!』(旧版 p.60より)
ところが、この分離降昇調って、日本の本にはまず説明がない(そもそもイントネーションについての説明があまりないから)。
いやいや、これ、BEじゃいっぱい使われるからこそ、説明が必要です![]()
そしてだからこそ、使いこなせるようになりたいもの![]()
というわけで、この『もっと』ではこの降昇調類を「禁断のイントネーション⁉ 降昇調と分離降昇調」って章で説明してます![]()
![]() 日本では、これほど踏み込んだ本はないです
日本では、これほど踏み込んだ本はないです![]()
でも、これがBEらしさ。
そこは避けて通れないもの。
その降昇調に触れないBE発音じゃ、まったくBE発音にならないです![]()
そして、これを説明できるということは、使えるようになるための、第1歩なのです。
イントネーションはただ真似て覚える、じゃあ使いこなせるようにはならない![]()
英国に住んでいて、ネイティブに囲まれていて、たくさん英語に触れていれば、それでも使い方を覚えていけるでしょうけど![]()
![]()
でもそういう環境にいないのなら、理屈で説明できることが必要![]()
![]()
どこで下がって、どこで上がるのか。
なぜ下がって、なぜ上がるのか。
そこらへんがきっちり説明されていないといけない。
上記の文なら、なぜhopingで下降調になったのか![]()
なぜほかの単語じゃなくて、hopingなのか![]()
そして、なぜyouで上がるのか![]()
![]()
![]()
その説明もなく、ただ真似て覚えろ、じゃあダメ![]()
![]()
これ、会いたいと思っていた人に、バッタリ会えたときのイントネーション。
この状況では、このイントネーションにならざるを得ないのです。(より詳しくは『もっと』を参照してください。)
ちなみに、イントネーションをよく理解していないと、この文を聞いて、単なる上昇調と思っちゃうかもしれないです![]() ヤベっ!
ヤベっ!
でも、そうじゃない![]()
まあ、もし上昇調ととらえたとしても、AEの上昇調とは、全然メロディが違ってしまうということです![]()
そこを踏まえて上昇調と言うならいいですけど![]()
BEのイントネーションを扱うときは、文全体の音程の変化に敏感にならないといけません![]()
ちなみに、理屈で説明できるからこそ再現性があるわけです。
学習者自身が使いこなせるようになれるということです。(ただし個人差があります(笑))
これ、例の絶版になってしまった、幻の名著(笑)『理屈でわかる英語の発音』から言い続けていることです。
だからこそ、この『もっと』は『理屈』の発展形なんです![]()
あ、最近は執筆で休んでいたストアカ講座、近日中に復活させます。BEイントネーションの講座もやります。